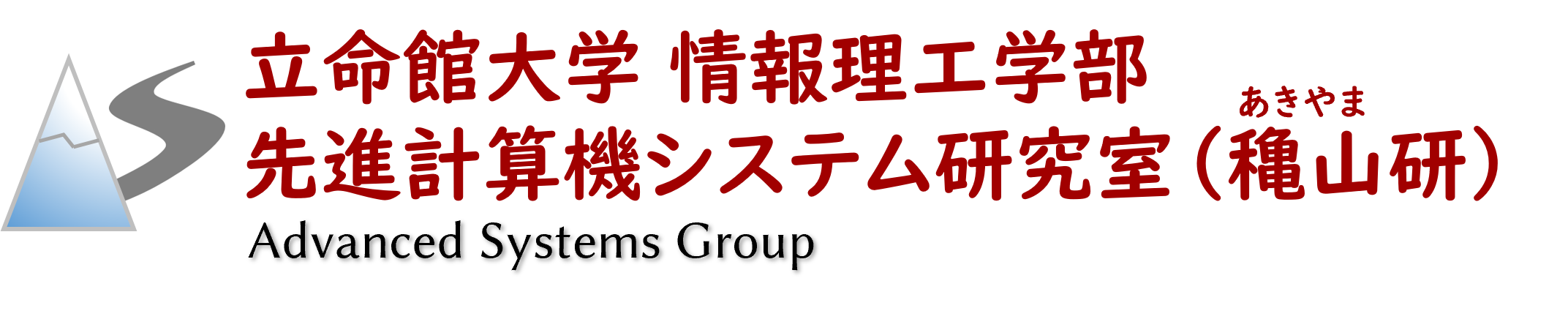For B3 Students
配属ガイダンスで使ったスライド
こちら(立命館アカウントでのログインが必要)
2025 年の研究室見学日程は?
- 穐山と学生による研究内容紹介
- 日程:6/2, 6/4, 6/6 の 5 限
- 内容:具体的な研究内容について穐山と研究室の学生が説明し、その後質問を受け付けます。学生の研究内容紹介は毎回変わりますので何度でも来てもらってかまいません。具体的な発表内容は上記スライドの最終ページを見てください。
- 学生座談会
- 日程:6/5, 6/10 の 5 限
- 内容:研究室の学生のみでみなさんの質問に答えます。教員はいませんので聞きにくいことも自由に聞いてください。
研究テーマはどうやって決めるのか?
研究テーマは自分で見つける場合と教員から候補を提示する場合の両方があります。 自分で強くやりたいテーマを持っている場合はそれに取り組んで欲しいです。 もちろんその場合も教員と密に議論しながら進めます。
しかし学部生や修士学生で自ら研究テーマを見つけるのはたいていとても困難です(下の方の「研究とは何か?勉強や開発とはどう違うのか?」を読めば難しさが分かると思います)。 そこで教員からテーマ候補やその種となるアイディアの提示も必要に応じ行います。
日々の研究生活はどのように進むのか?
日々の研究生活は 1. 全体やグループでのミーティング、2. 輪講会、3. English Workshop (EWS)、4. その他の時間で構成されます。 1, 2, 3 は週一回の予定ですが、具体的に何曜日の何時かは未定です。
- 全体やグループでのミーティング:研究の進捗や直面している課題を他のメンバーと共有し、議論します。 またテーマが近いメンバー同士で小グループを作りより密な議論を行う場合もあります。
- 輪講会:持ち回りで論文を読み発表したり技術的なチュートリアルを行います。自己の研究テーマに閉じない幅広い知識やプレゼンテーション能力を身に着けることが目的です。
- English Workshop (EWS):日常の気付き、趣味、旬の話題などの議題を持ち寄り、それについて英語で楽しくお喋りします。 英語運用能力と英語による相互理解能力を高めることが目的です。 将来的には情報システムグローバルコースの研究室と合同での開催を狙っています。
- その他の時間:上記イベントがない時間は休み時間ではありません。 研究をしっかりと進めるためには他の授業がない時間は全て研究にあてる必要があります。 なお平日に毎日きちんとやり土日祝日は休むスタイルを推奨しています。
当研究室が他研究室と比べ特別忙しい or 暇ということはないと思います。 上の中では 3. EWS が他研究室と比べユニークな点かと思いますが、 1, 2, 4 はどこでも同じような雰囲気でしょう。
コアタイムはあるか?
コアタイムは特に設定していません。 ただし自宅で集中するのは多くの人にとって難しいので、できるだけ研究室に来ることを推奨しています。
研究室の設備にはどのようなものがあるか?
まだ新しい研究室ですが、積極的に研究環境を整えています。 現状では以下のような設備があり、また研究活動に必要なものの購入リクエストも可能です。
- 研究用物品
- 研究室内データセンタ(Intel Xeon Platinum CPU、NVIDIA のサーバ用 GPU など)
- 1 人 1 台の自作 PC、使いたい人には 1 人 2 枚以上のディスプレイ
- 各種 FPGA ボード
- 1 枚で 128 GB もある不揮発性メモリの実機
- OS、セキュリティ、メモリシステムなどの計算機システムに関する各種書籍
- 生活用物品
- 休憩用のソファ(写真はこちら)やハンモック
- コーヒーメーカー、冷蔵庫、電子レンジ
研究以外の楽しいイベントはあるか?
学生時代の友人や人脈は今後の人生にとって非常に大切だと考えているので、楽しいイベントもできる限りやりたいと思っています。 2022 年度は卒研室でボードゲーム大会をして交流を深めました(その時の様子はこちら)。 これに関しては特に皆さんからの提案を歓迎します。
また研究室外での活動として、京都府警サイバーセンターと共催で「アンチサイバークライムカフェ」というイベントを企画運営しています。 イベント内容の立案を穐山が、当日の司会進行を研究室学生が担当し、第一回を 2023 年 5 月に行いました。 来年以降も継続予定で、興味があれば内容の立案など全てに関わることができます。 当日の様子は下のツイートを見てください。
5月13日(土)、京都府警察本部サイバーセンターと立命館大学情報理工学部は、サイバー犯罪被害防止について、学生がアイデアを考えるイベントを開催しました。学生のみなさんはチーム一丸となって取組み、独創的な広報啓発活動のアイデアの発表が行われました。#アイデアソン #ACC2023 pic.twitter.com/5fv9l5YLWc
— 京都府警察サイバーセンター (@KPP_cyber) May 15, 2023
大学院進学と就職で迷っている
基本的には修士までは進学することをおすすめしています。 現代の科学技術は高度に発展・複雑化しており、大学 4 年間で学べることはそのほんの一部です。 大学院で特定のテーマにより深く取り組むことで、最先端の科学技術により近づくことができます。 また大学院まで修了し高度な知識を得ると就職の幅も広がります。 詳しくは情報理工学研究科による情報や、SN コース上山先生による文章を見てください。
なお念のため断っておきますが進学を強要することはありません。 また博士まで進学するべきかどうかは個々人の将来設計に大きく依存すると考えているので一概には言えません。
おまけ 1:研究とは何か?勉強や開発とどう違うのか?
研究とは「世界の幸福と発展に寄与するため、何らかの新たな事実を明らかにすること」だと思っています。 一方、勉強はすでに確立された知識を学ぶこと、開発は何らかの目的のためにシステムなどを作ることです。
研究のために勉強や開発が必要な場合がありますが、勉強・開発だけで終わってはいけません。 大学で行う活動は研究である必要があるからです。 例えばサイドチャネル攻撃を防ぐためのキャッシュ構造の研究には、 サイドチャネル攻撃の動作原理の勉強や提案するキャッシュ構造のシミュレータの開発が必要になるでしょう。 しかしこれらは手段であり、サイドチャネル攻撃の防止について何らかの新たな事実を明らかにするという目標を忘れてはなりません。
逆に研究のためには必ずしも開発が必要なわけではありません。 例えば新しいアプリケーション分野でメインメモリがどの程度性能のボトルネックになるかを調べるとします。 これには既存のアプリケーションコードやシミュレータを使えば十分で、開発はほとんど必要ないかもしれません。 そうだとしても、新たな事実が明らかにされればこれは立派な研究になります。 この意味でいわゆる「文系」(私は「人文科学」と呼びます)の学部での活動も我々の活動も本質は同じです。
おまけ 2:ロゴは何?
Advanced Systems の A と S を図案化しました。 A が高い山、S がそれに続く道で、研究目標という山に登る道筋を表しています。